
「ヒップホップ、R&Bから探るNBAとブラック・ミュージックの親和性」NBA・Rakuten WINDY CITY BLUES MUSIC 2020年
音楽業界への参入が一般化した21世紀のNBA。2020年代に突入した新世代“ミュージック・ボーラー”たちの挑戦。
NBAとヒップホップの熟成した関係
21世紀以降のNBAとブラック・ミュージックは、もはやその関係を前提として話が進められるまでになった。人気選手がラッパーとして楽曲を発表したり、大物ラッパー/シンガーがNBA選手と接近することは珍しくない。シャキール・オニールやクリス・ウェバーも出演した映画『Uncle Drew』(2018年)にてシンガーとしての才能も持つカイリー・アービングが主役を務めたことも記憶に新しいが、そのカイリーが現在所属するブルックリン・ネッツといえば、一時期ジェイ・Zが共同オーナーを務めていたこともある。
NBA選手の音楽活動は、自主制作のミックステープを出したり、配信リリースができるようになってから、敷居も低くなった。2007年にフランス語のラップでアルバムを出したトニー・パーカーをはじめ、メッタ・ワールド・ピース、スティーブ・フランシスなどラッパーとしての作品を残すプレイヤーは多い。スティーブン・ジャクソンはStak5を名乗り、「Lonely At The Top」(2012年)にケビン・デュラントを招いていたが、そのデュラントも「Tha Formula」(2012年)などでボーラーにとどまらない才能を見せてくれた。
ルー・ウィル名義で多くの曲を出しているルー・ウィリアムズが在籍チームの本拠地を代表するラッパーやプロデューサーと絡んできたのも興味深い。ルーといえばシックスマンとしての活躍で知られるが、トロント・ラプターズを地元ファンとして応援するドレイクが「6 Man」(2015年)を書き贈るというラッパーからボーラーへのアンサーも、NBAとヒップホップの関係が成熟した証として胸が熱くなる。
NBA・Rakuten WINDY CITY BLUESより引用 → 続きはこちらより
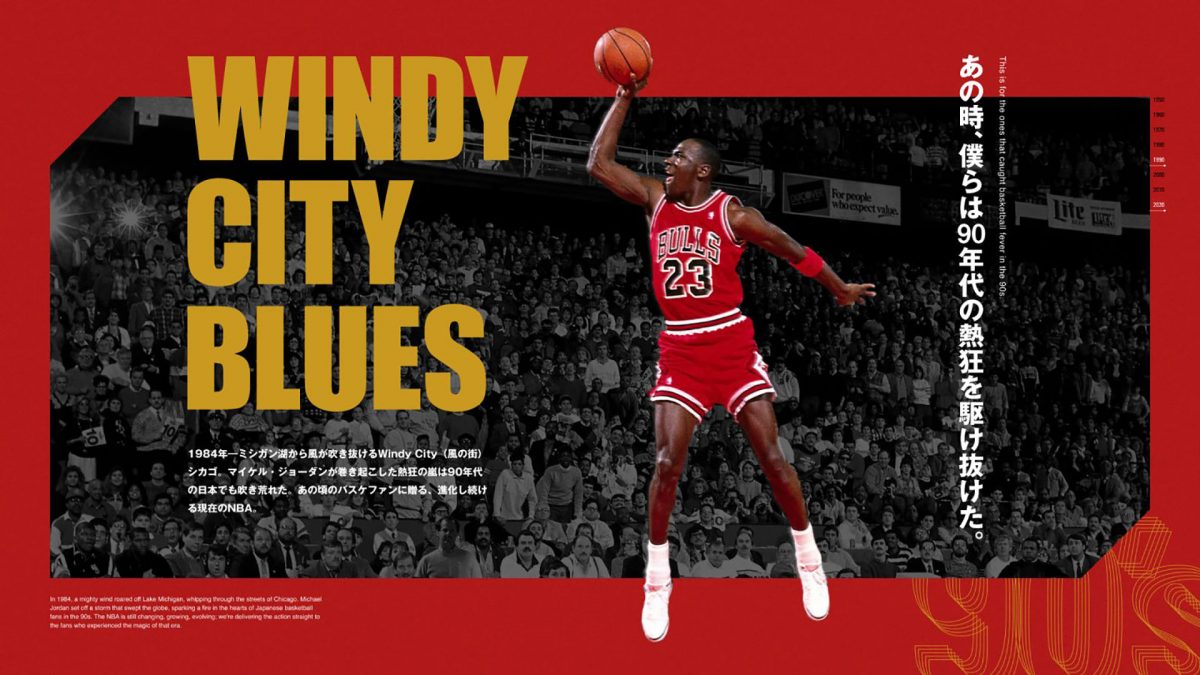
- NBA・Rakuten WINDY CITY BLUES MUSIC 2020年



